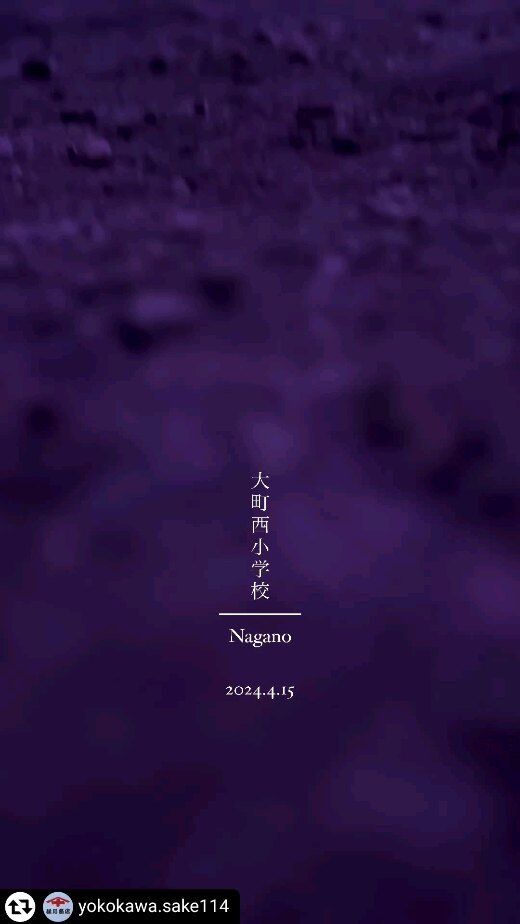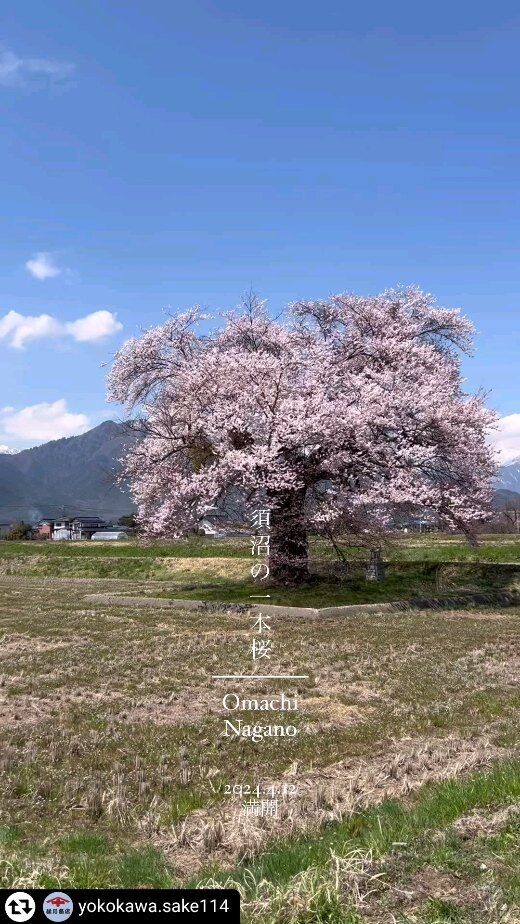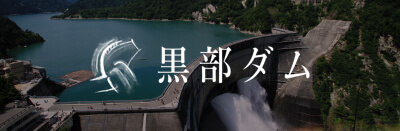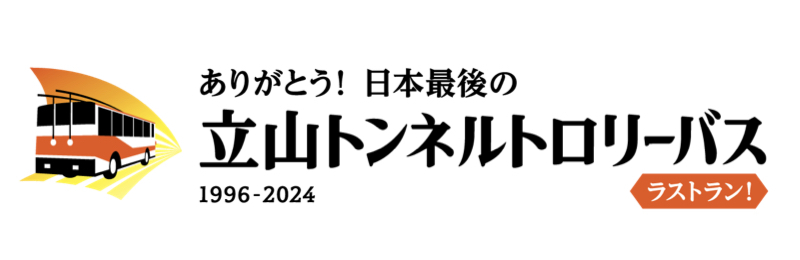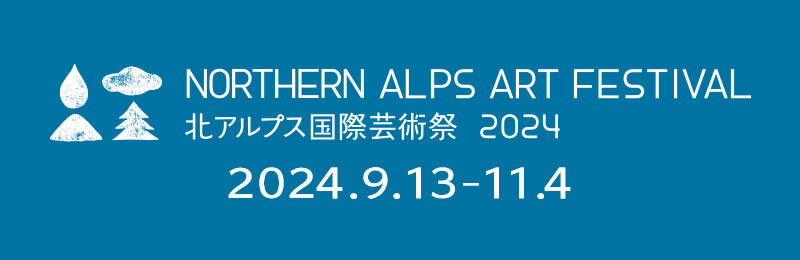STORY

はじまりは
許可条件の一文から
トロリーバス誕生ストーリー
黒部ダムを国立公園特別地域内に建設する際の厚生省(当時)の許可条件に、「エ事用として建設される道路は工事竣工後はこれを公衆の利用に供すること」という一文がありました。そこで検討の結果、長いトンネル内に排気ガスが充満せず、環境にやさしいトロリーバスで旅客輸送を行うこととなりました。

トロリーバスを走らせるために必要な工事を行うため、多くの許可申請を行い、昭和38年に着工。工事は急ピッチで進められました。黒部川第四発電所管理事務所も発足し、運転と保守の要員養成を大阪市交通局で行い、昭和39年8月1日、運行が始まりました。当時は黒部ダムの竣工後の残工事の風景が見え、駅舎も簡素で、黒部ダムの観光ルートも現在とはまったく違うものでした。

トロリーバスは3代。
トロリーバスの車両は初代の100型から200型へと移り、平成5年から300型が登場。
1964年(昭和39)8月1日に営業運転を開始以来、54年間無事故で、61,624,737人ものお客様を運びました。そして2018年11月30日に最終運行を迎えたのでした。







後を引き継いだ電気バス
2019年からは、CO2を排出しない環境にやさしい電気バスが運行を開始。電気バスのデザインは、関電トンネルトロリーバスが運行開始から54年間無事故を継続してきた安全運転への強い思いと使命感が継承する思いを込めてデザインで踏襲しているものです。
電気バスは、ディーゼルバスからエンジンを取り外し、駆動用モーターおよびリチウムイオンバッテリーを4パック搭載しています。充電は車載パンタグラフ方式を採用し、1往復ごとに扇沢駅のホームにて約10分の超急速充電を行っています。












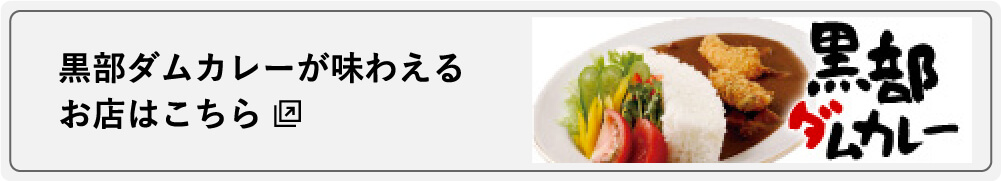






![
開催まであと5ヶ月
北アルプス国際芸術祭2024
@northern_alps_art_festival
2024.9.13~11.4
大町市(信濃大町)全体を使い、3年に1度開催している「北アルプス国際芸術祭」。
今年は、10の国と31組のアーティストが参加します。
特徴ごとに大町市内を5つのエリアに分け、それぞれの魅力を引き出した作品が展示され、週末を中心に様々なパフォーマンスも開催されます。
今から楽しみです!!!
北アルプス国際芸術祭って?と思った方は、
とりあえず過去2回の芸術祭の投稿をご覧下さい⬇
#北アルプス国際芸術祭2017
#北アルプス国際芸術祭2020-2021
先週末、作品作りに必要な素材を集めがあったようです。
これからたくさんのアーティストさんが訪れ、芸術祭に向け準備を進めて行きます。
できるだけ多くの方に参加していただき、作品を作る楽しみも感じていただけたらと思います。私達も参加する予定です。
芸術祭実行委員会だは、一緒に芸術祭を盛り上げてくださる方を募集しています。
前売り券の販売も始まっていますよ~!
⚠今年度は、水曜日定休です。
こちらでも、これから芸術祭のこともご案内していきます。
#立山黒部アルペンルート#黒部ダム へお越しの皆様も、ぜひ大町市へお立ち寄りくださいね🙇🏻♀️ ̖́-
.もちろん#アート好き さんも
#信州#長野#北アルプス#登山
#芸術祭好き#art
.
.
.
.……………………………………………………………………………………………………
北アルプス国際芸術祭2024
詳しくはこちら⬇
@northern_alps_art_festival
………………………………………………………………………………………………………
repost - @northern_alps_art_festival
[作品制作レポート|竹切り出し]
2024.4.14
台湾在住の参加作家 ヨウ・ウェンフー〈游文富〉さんが来日し、作品に使用される竹の切り出し作業を、作品が展示される八坂地区の皆さんとボランティアサポーターの方々と一緒に行いました。
快晴でとても暑い中でしたが、集中力が切れることのない作家さんの真剣な眼差しや八坂地区の皆さんの手際の良い作業がとても印象的でした。
これからどんな素敵な作品が出来上がるのか皆さんぜひご期待下さい!
暑い中参加いただいた皆さん、ありがとうございました!
これから作品制作がスタートしていきます。一緒に芸術祭を盛り上げていただけるボランティアサポーターを随時募集中です!
video by Hirabayashi Takeshi @belca_d
___
北アルプス国際芸術祭2024
会期:2024年9月13日(金)-11月4日(月・祝)*会期中水曜定休
会場:長野県大町市
Northern Alps Art Festival 2024
Venue: Omachi City, Nagano, Japan
Dates: September 13 (Fri) - November 4 (Mon), 2024
https://shinano-omachi.jp/
___
#北アルプス国際芸術祭 #北アルプス国際芸術祭2024
#長野県 #大町市 #長野 #大町 #信濃大町 #北アルプス #アート #芸術祭
#NorthernAlpsArtFestival2024 #NorthernAlpsArtFestival
#nagano #omachi #japan #art #artfestival
#北阿爾卑斯國際藝術祭 #北阿爾卑斯國際藝術祭2024 #阿爾卑斯 #藝術祭](https://kanko-omachi.gr.jp/wp/wp-content/uploads/sb-instagram-feed-images/438798545_446035834478207_1251327221894324094_nfull.jpg)