教育・団体旅行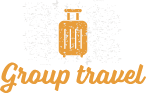
No.4 青木湖で学ぶ水力発電と北アルプス地域の灌漑農業の歴史
大町市の鹿島川の水は雪解け水により、他の河川と比べると水温が10℃も低いため農業用水としての利用に支障があった。この問題を解消するため、昭和29年、鹿島川から取水し青木発電所を経て青木湖に水を流入させ温度上昇後、水をくみ上げて鹿島川流域の農地に配水する灌漑農業が行われるようになった。
学習プログラムの
ポイント
Point
全国的にめずらしい水利システムを見学
Point
農業の歴史から灌漑施設の必要性を理解する
Point
水や鉄など生活に必須な資源の循環を考える
プログラムの流れ
- 灌漑施設の概要説明
- 青木湖発電所見学(青木湖発電所見学20分)
- 移動30分
- 大出頭首工見学(施設見学30分)
- 移動15分
- 常盤発電所見学(発電所見学20分)
- 移動15分
- 株式会社レゾナック・グラファイト・ジャパン大町事業所歴史記念館見学(記念館見学30分)
| 実施可能時期 | 5月15日~10月31日 |
|---|---|
| 所要時間 | 3時間程度 |
| 対象 | 小学生・中学生・高校生 |
| 対応可能人員 | 40名 |
水資源を活かし、地域に貢献する仕組みを学ぶ
国内屈指の水利システムを見学
- 生活を支える施設で地域の水循環を考える
- 豊富な水を有効利用する苦労や知恵を学ぶ
-
地域の水を、農業用水、発電用水に使用する産業財産とも言えるシステムです
-
発電所内部を見学し理科を深めます
-
高瀬川沿岸用水は高瀬川及び農具川から取水して大町市、松川村、池田町、明科及び安曇野市までの高瀬川両岸の水田地帯へ農業用水を供給します。写真は、灌漑設備の基幹的農業水利施設「大出頭首工」です
大町市の暮らしを支える北アルプスの雪解け水。水温が低すぎて農業用水には不向きと言われた水を有効利用するため、昭和29年から運用されているのが、灌漑施設を組み込んだ水利システムです。取水口となる鹿島槍ヶ岳の小冷沢から下流の広津発電所までは全長36Km 、高低差は700m。本プログラムでは、水害対策などの役割も併せ持つ施設の見学を通じ、未来の水循環を考えます。
グローバルに展開する黒鉛電極事業
- 鉄のリサイクルと脱炭素に貢献する黒鉛電極
- 持続可能な社会の発展に貢献
生活に欠かせない鉄。その大切な鉄を循環させる技術として黒鉛電極を活用した電気製鋼炉による鉄のリサイクルがあります。効率的で環境にやさしい鉄のリサイクルを促進し、持続可能な社会の発展に貢献します。
経済成長を支える化学の力を実感
- 経済成長に欠かせない国内技術に触れる
- 効率的でエコな鉄リサイクルを考える
レゾナック・グラファイト・ジャパンの事業所内にある歴史記念館を見学します。高度経済成長を支えた、国内初となるアルミニウムの製造にはじまり、グローバルに展開する黒鉛電極事業など、社会を支えてきた化学の力を学びます。
探究学習の流れ
Step
事前学習課題の明確化

農業を行う上で水は欠かすことができない存在です。灌漑施設とは何かを調べ雨量が多い日本において何故、灌漑農業が必要だったのかを考えてみましょう。また、灌漑農業がもたらす水循環や経済効果などについて考えてみましょう。
Step
現地学習答えを導く

青木湖を利用した灌漑施設の見学により、灌漑施設の必要性について理解し、健全な水循環の形成に向けて皆さんが出来ることについて考えてみましょう。
Step
事後学習掘り下げる

日本の食料自給率は約40%です。言い換えれば輸入先の国々の農業用水を使用して豊かな食生活を送っています。このような中、世界が直面している水を巡る課題の解決に向けて皆さんが行えることについて堀り下げて考えてみましょう。









