教育・団体旅行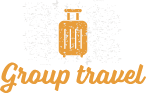
No.6 「水が生まれる大町」の 水を生かした街づくりと塩の道の宿場町の歴史探訪(大町市観光ボランティアの会)
大町市は平安時代後期から約500年この地を治めた豪族・仁科氏によって、北アルプスの生み出す真水に近い豊富な水資源を利用した治水・利水の灌漑工事が進められ、計画的に作られた町です。中心市街地の整備は1300年代(室町時代)からすすめられ、長い年月をかけて整備された水路を辿り、塩の道の宿場町の歴史を探訪し、水の恵みを考えます。
プログラムの流れ
- 塩の道ちょうじや
- ポケットパ-ク水路
- わちがい(男清水・女清水)
- わちがい横路地
- 麻倉
- 道祖神
- 大澤寺
- 竈神社
- 道路原票
- 追分
- 大黒天
- 若一王子神社
- 立体交差水路
- 北アルプスブルワリー
- 市野屋
- 旧對山館
- ケンカ横丁
- 皇大神宮・西宮神社
- 塩の道ちょうじや
| 実施可能時期 | 4月~12月 |
|---|---|
| 所要時間 | 2時間又は3時間 |
| 対象 | 小学生~高校生 |
| 対応可能人員 | 20名程度 |
探究学習の流れ
Step
事前学習課題の明確化

皆さんの居住地域の歴史と水道がどこの水を使い、どのように処理されて家庭に届いているか調べてください。
Step
現地学習答えを導く

雄大な北アルプスからの恵みであり、700年も前からこれを活用して街を成り立たせた水路を辿り、塩の道の宿場町の歴史を辿ることにより、人間が生きるために欠かせない水と塩の大切さを考えます。
Step
事後学習掘り下げる

生活に欠かせない水の大切さと、再生可能エネルギーである水について考えます。







